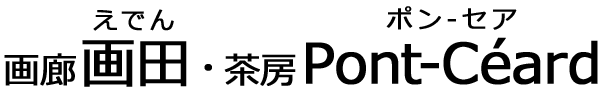間もなく五十路を向かえるような人間にとって、秋でもないのに「夜が長い」。「満腹酒」の後の寝付きは1分とかからないのだが、そうでない時の眠れないのには閉口頓首である。深夜のテレビもあまり所望でない。ニュースも「千遍繰り返し」で新鮮味がない。
そうなると頼れるのはやはり読書しかない。このところ、学生時分に読んだ小説をまた買い求めて「じっくり」と読み返したい衝動に駆られるから、不思議だ。小生の贔屓作家の一人、川端康成(1899-1972)は1968年にノーベル文学賞を受賞した言わずもがなの大物である。1899年(明治32年)に大阪の開業医を父として生まれたが、その生い立ちは厳しく、2歳で父が、3歳で母も他界、1912年の13歳までに祖父母と姉も相次いで亡くし、天涯孤独の孤児環境で育った。新潮文庫の「伊豆の踊子」の裏表紙には「二十歳の旧制高校生である主人公が孤独に悩み、伊豆へのひとり旅に出かけるが、途中旅芸人の一団と出会い、一行中の踊子に心を惹かれてゆく。人生の汚濁から逃れようとする青春の潔癖な感傷は、純粋無垢な踊子への想いをつのらせ、孤児根性で歪んだ主人公の心をあたたかくときほぐしてゆく。雪解けのような清冽な抒情が漂う美しい青春の譜である。」とある。
「伊豆の踊子」は1926年に発表された。「道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追って来た。」ではじまる。「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。」の書き出しは1935年の「雪国」である。
「伊豆の踊子」の主人公である「私」が好意を寄せた「踊子」は14歳の「薫(かおる)」である。興味あることに本文の38ページ中、2箇所しか「薫」はなく、その他はすべて「踊子」である。「踊子」の名が「薫」と分かるのも19ページ目に至って、兄である栄吉が「私」に告げている。「雪国」の「女」は新潮文庫の本文169ページ中の45ページではじめて「駒子」となり、その後は「駒子」で通される。それも「今朝になって宿の女中からその芸名を聞いた駒子も・・・・・」とある。些細で陳腐なことかもしれぬが、小生にはこの川端康成的小説構成が何かしら気になりしょうがない。
ノーベル賞の受賞理由は「日本人の心情の本質を描いた、非常に繊細な表現による、彼の叙述の卓越さに対して」である。「初夏の夜長」、昔に帰って日本文学の真髄に浸るのも満更でもない。
川端康成は「」伊豆の踊子」の執筆に4年半をかけた。終盤に「「町は秋の朝風が冷たかった。栄吉は途中で敷島四箱と柿とカオールという口中清涼剤とを買ってくれた。「妹の名が薫ですから」と、微かに笑いながら言った。」」とある。巨匠も「ギャグ」を飛ばしているのが、何とも嬉しい。