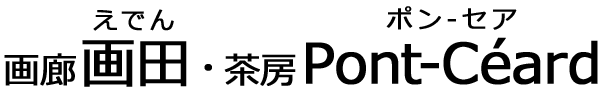●武士は通常、ふたつか三つの名前があったんですね。坂本竜馬の例では、「幼名(通称)」が「龍馬(竜馬)」、正式な手紙などの署名で使用する「諱(実名)」が「直陰(なおかげ)」「直柔(なおなり)」、絵や誌をかいた時などに使用する「号」が「自然堂」、脱藩した時などの隠れ蓑とする「変名」が「才谷梅太郎」となる。(龍馬の手紙では「諱」が使われた例は少ない)。(女子には諱を付けないこともあった)。そこで「諱」(いみな)だが、「忌み名」の意。「『諱』という漢字は、日本語では『いむ』と訓ぜられるように、本来は口に出すことがはばかられることを意味する動詞である。この漢字は、古代に貴人や死者を本名で呼ぶことを避ける習慣があったことから、転じて人の本名(名)のことを指すようになった。」(Wikipedia)。本名は「真名(まな)」とも。そうそう、諱はその人の生涯の幸福を祈願して好い音義を選んで付けたそうですが、それは元服の時のようです・・・から・・・「名は体を表す」なんていいますから、今よりは実用にあっていますね。名前負けしているとか、実物とかけはなれた大仰な名前なんてよくありますからね・・・元服は今の中学生ですから、ある程度は自分で判断して付けることが可能ですね。戸籍の登録など事務が煩雑かもしれませんが、一考には価しませんかねぇ~。1月20日。
●この度は歴史小説を読む時にいつも気になっている「幼名」と「諱」(いみな)について考えてみるか。例の「万柳」に、生まれた孫子に提案した名前が蹴られたので犬猫につけた・・・という意の川柳が載っていた。確かに最近の犬猫の名前は人と変わらないようなものがある。今に言うところのきらきらネームであろうか。そもそもこのきらきらネームを最初につけたのはだれであろうか。その前に「変な」名前をつけたので有名なのが織田信長であろう。長男の忠信(たたのぶ・本能寺の変で死去)の幼名は「奇妙丸」、次男が「茶筅丸」(信雄=のぶかつ)、三男が「三七」(信孝)、四男が「於次」、五男が「坊丸」、六男が「大洞」(通称「三吉」)、七男が「小洞」、八男が「酌」、九男が「人」、十男が「良好」、十一男が「緑」というから、ふざけているのやら・・・ちゃんと真剣に考えなかったのは確かだろう。その信長の最も寵愛した近習(小姓)の蘭丸(「乱丸」が正解か。「信長公記」にも「森乱」とある)の場合、父の森可成(通称が三左衛門)の付けた幼名は、三男の蘭丸(成利・司馬遼太郎「覇王の家(下)」では次男とある。p78)、四男が坊丸(長隆・本能寺の変で死)、五男が力丸(長氏・本能寺で死)、六男が千丸(忠政)・・・これもちょいこら好い加減か。近代では明治の森鴎外の名付けが一目置かれ、これこそきらきらネームの発祥ではと言われているようだ。上から、於莬(おと)、茉莉(まり)、杏奴(あんぬ)、不律(ふりつ)、類(るい)とくる。つづく。1月19日。
●司馬さんの小説には電子辞書が必須だ。持って移動すのは面倒なので机の前と寝床に一つずつ置いている。司馬作品のページ順にまとめた「字引」が電子辞書にあると楽だと思うくらいだ。「余談ながら」をもうひとつ。「余談ながら、秀吉はのちこの鬼武蔵の最期を悼み、その生母に情愛のあふれる手紙を書き送っている。鬼武蔵がこのとき乗っていた『百段』は、槍傷を二カ所受けたが、その後も生きながらえ、なんと三十年後の大阪冬・夏の陣にも、この馬は鬼武蔵の子の森忠政をのせて戦場を駆け、のち作州津山(徳川期の森家の城下町)に葬られたという。作州にはこの馬のための小さな祠まであるという。筆者はそれを津山でさがしたが、実見することができなかった。」(前出の「覇王の家・下」pp150~151・長久手の戦いで家康の手の鉄砲で射殺された鬼武蔵こと森武蔵守長可=ながよしがのっていた馬「百段」)とあるように、司馬さんの現地調査はいつも軽快である。このくだりは『柏崎物語』『四戦紀聞』『小牧陣始末記』の資料をもとにしている。「余談ながら」もあるが「この男の癖で」とか「もっとも○○自身のおもしろさは」での司馬さんの人物批評がこれまたおもしろい。司馬さんは造語も巧みである。司馬さんが主人公を絞って構想を練りペンを持ったそのときは、もうその時は主人公になりきっていた・・・と何かで読んだが・・・そうであるからして臨場感あるその場面を自由自在な言葉表現でわれわれに示してくれているのであろう。感謝、感謝だ。「竜馬がゆく」がまた読みたくなった。1月17日。
●親交の厚かった作家で僧侶の寺内大吉氏が「海音寺潮五郎さんは、よく「司馬君はどこであんな文体を身に着けたのだろうね」とおっしゃっていた」と、義弟の上村洋行氏に教えてくれたという。上村氏はそれを「余談ではあるが」だという(文藝春秋2016年2月号・p161)。譬えば、「余談ながら、秀吉は死後神になることをのぞみ、その旨朝廷に内奏して豊国大明神という神号を得たが、家康はそのことまでまねをし、東照大権現という神号を得た。大明神の創造性は大権現の模倣性によってひきつがれるのである。」(司馬遼太郎「覇王の家」(下巻)・p66・新潮社)といった具合にである。文化部(寺社関係)の記者だったため宗教用語などに強い。そして何より語彙がやたらに豊富で、さらにさらに人物の深遠なる心情表現が絶後の魅力ではないか・・・もちろん物語の計り知れない数量・・・と私は思います。1月17日。