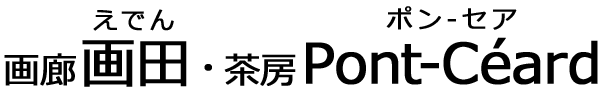●「司馬遼太郎(1923~1996)のこと」
▼わたしが司馬遼太郎記念館(東大阪市下小坂・最寄り駅=奈良近鉄線の河内小阪駅/八戸ノ里駅・安藤忠雄設計)を訪問したのはちょうど3年前の7月でした。ボランティアで案内をしているリタイヤの人が数人いるようでしたが、そのひとりの方と椅子に座って司馬さんを語っていた時、何かのことで司馬さんの遺族の話題になりました。司馬さんがバツイチでひとりの息子さんがいたということが、司馬さんの死後、新聞で騒がれたと云うのです。と云うのも、司馬さん死去の直後の大阪の長者番付に突然身元が分からない若い人が現れたそうで、調べるにその方が司馬さんの息子さんだったという話です。周囲には限られた人しかしらない秘匿の過去歴だったのでしょう。皆がびっくりしたとのことでした。
▼司馬さんの結婚歴を紹介すると
①1950年(昭和25)、大阪大学医局の薬剤師と見合いにより最初の結婚。
②1952年(昭和27)、長男が誕生。
③1954年(昭和29)に離婚。長男は実家の福田家に預けられ祖父母が養育。
④1959年(昭和34)、同じ産経新聞記者の松見みどりと再婚。福田(旧姓松見)みどり(1929~2014)氏との間には子供はいない。生涯浮いた話もなかったと云う。
▼巣ごもり生活、書棚の目に入った「司馬遼太郎が考えたこと・Ⅰ」をぱらぱらめくると、「魚ぎらい」というエッセイが目に留まり、司馬さんの魚嫌いの半端でないことが知れました。司馬さんは池波正太郎さんとも懇意だったそうですが、池波さんほどグルメでなかったのはその類の書き物がないことからも容易に想像できます。京都の先斗町に1952(昭和27)年創業のおばんざいの老舗、「ますだ」があります。司馬さんも贔屓客のひとりで、新聞記者時代からの常連、亡くなるまで年に数回来店していたようです。店内に飾られている扁額や屛風は司馬さん直筆です。その「ますだ」にわたしも一度足を運んで鱈腹呑んだことがります。店内の壁に「おひとり様、徳利2本まで」と貼られてあるのですが、店主は「お客さんならもう2本は大丈夫です」と言われた記憶が残っております。
▼その「魚ぎらい」のなかに、「女房をもらうとき、彼女はなんと魚は見るのもきらいだということがわかった。これだけでももらう価値があると、私は確信した。差しむかいで魚をバリバリと食われては、まるで食人種と食卓を囲んでいるようで想像するだにゾッとしていたのである。」・・・・・・また、新婚旅行で訪れたひなびた海辺の旅館でだされた近海の上物の鯛に、「きょう宴が始まる前に二人がまずしたことは新聞紙をとりだすことであった。ソッとタイをくるみ、窓から海辺へぬけだして、波のかなたへすてたのです。」・・・・・・と綴られてありますから、司馬さんのそれこそ筋金入りの魚ぎらいが伝わります。
▼そこでわたしの興味の「本題」なのですが、この新婚旅行のお相手は二人のうちのどちらだったのか。この「魚ぎらい」のエッセイが掲載されたのが「たべもの千趣・第二十号」(筆者名は本名の福田定一)で1960年(昭和35)年1月1日です。普通なら10年前のそれも離婚した人のことを書くことはまずないでしょうし、1960年は福田みどり氏との結婚の翌年ですから、これはやっぱり後者との新婚旅行と察するのが妥当でしょう。
▼巣ごもりの何ともたわいのない譚と一笑に付されそうですが、贔屓のひとの秘密を持ち抱いたようで、なんともウフフッの気分になれますから、それだけでもコロナ禍のなか、「憂きがなかにも楽しき月日を送りぬ」なのです。呵呵!!!
※Wikipediaなどに司馬さんの私生活が載るようになったのは、つい最近のことです。
7月31日。
 1891年(明治24)には正四位が贈られているくらいですから。ついでながら山岡荘八の「坂本龍馬」は1956年の作品ですから、もしかしてみどり夫人はこの荘八の龍馬を読んで知っていたかもしれ
1891年(明治24)には正四位が贈られているくらいですから。ついでながら山岡荘八の「坂本龍馬」は1956年の作品ですから、もしかしてみどり夫人はこの荘八の龍馬を読んで知っていたかもしれ 「坂本龍馬伝・汗血千里の駒」です。これは明治16年、高知の土陽新聞に発表された連載小説です。極めつけは1901年、皇后美子さまの夢枕に龍馬が登場し、「微臣ハ坂本龍馬ニ候ガ、私ガ海
「坂本龍馬伝・汗血千里の駒」です。これは明治16年、高知の土陽新聞に発表された連載小説です。極めつけは1901年、皇后美子さまの夢枕に龍馬が登場し、「微臣ハ坂本龍馬ニ候ガ、私ガ海 →それ以前の「近世報国赤心士鑑」の序列でも来島又兵衛、久坂玄瑞に次いでおり、高杉晋作は龍馬のひとつ下位でした。このように龍馬が「竜馬がゆく」の前は全くの無名ではなかったの
→それ以前の「近世報国赤心士鑑」の序列でも来島又兵衛、久坂玄瑞に次いでおり、高杉晋作は龍馬のひとつ下位でした。このように龍馬が「竜馬がゆく」の前は全くの無名ではなかったの 次なる小説のテーマを相談したところ、坂本龍馬を是非といわれたそうな。帰ってみどり夫人に云うと、なんと夫人は龍馬を知っていたというのです。そして最初の一項を読んだ時、夫人は
次なる小説のテーマを相談したところ、坂本龍馬を是非といわれたそうな。帰ってみどり夫人に云うと、なんと夫人は龍馬を知っていたというのです。そして最初の一項を読んだ時、夫人は から、別に龍馬に詳しくなくても最後まで読破して、司馬さん創作の龍馬からその生き様を探求し、人生の指針のひとつとして活用すればいいのであります。当時産経新聞に高知出身の先輩
から、別に龍馬に詳しくなくても最後まで読破して、司馬さん創作の龍馬からその生き様を探求し、人生の指針のひとつとして活用すればいいのであります。当時産経新聞に高知出身の先輩 私が若い人に勧める本はと云うと、真っ先に司馬遼太郎の「竜馬がゆく」と「この国のかたち」です。今の日本人の龍馬像はこの小説に負うところが大きいのですが、小説ですからあくまで
私が若い人に勧める本はと云うと、真っ先に司馬遼太郎の「竜馬がゆく」と「この国のかたち」です。今の日本人の龍馬像はこの小説に負うところが大きいのですが、小説ですからあくまで