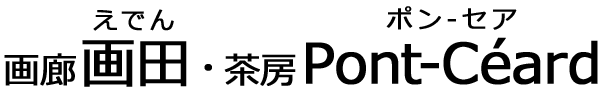●「食への貪欲さ・魯山人のこと」
▼魯山人を知らない料理人は潜りでしょうし、骨董好きで魯山人を知らないのは似非でしょう。北大路魯山人の器は古風で気品があり、それなりの腕前が拵えた料理でないと器に負けてしまいます。彼は各地から腕に覚えのある陶工を集め、彼自身は釉薬を選り絵付けをしたのです。その魯山人の著書に「料理王国」と云うものが残されています。
金の助「主人先生は久しぶりに実家へ帰られたそうで・・・・・・」
主人先生「そうだな、流石に盆での帰省は控えていたのじゃが、少しはコロナが落ち着いてきたし、両親ももう高齢じゃからの。いつ何が起こっても後悔しないように月に一度は顔くらい見せないとな」
金之助「そうですにゃん、健全な時にいろいろ話しておきたいことや訊いておきたいことも多ござんしょうにゃん。ところで帰る日の朝には近くの○○ネ○へ何やら買い出しに行かれたようで・・・・・・」
主人先生「そうじゃな、毎度のことじゃが田舎には鮮魚など生鮮ものが乏しいし、スーパーも農協系の一軒だけじゃからの。車の運転も容易ならん歳じゃからな。そうじゃ今日は魯山人の譚じゃたな。魯山人(本名:北大路房次郎)はもともと篆刻家で若い時には食客などした苦労人じゃな。1883年(明治16)の生まれで、吾輩の生まれた1959年(昭和34)に76歳で没したのじゃな。その陶芸(器)は相当な数量じゃからな『なんでも鑑定団』の常連じゃし、銀座の『九兵衛』に行けば展示もあるくらいじゃ。その『料理天国』のなかに鮎についての蘊蓄が割いてあるのじゃがな、前回7月初旬に帰省した折に食った『鮎寿司』の香味が忘れられないこともあってな、今回も鮎を用意してもらったのじゃ」
金之助「そうですか、鮎ですか、帰宅した時の千鳥の酔い加減から察するにさぞかし堪能されたようで・・・・・・」
主人先生「約2か月弱振りの実家じゃからの、そりゃもう。家飼の2羽の鶏の塩焼に鶏汁、それに鮎の背越しに鮎寿司に塩焼じゃた。鱈腹のつもりじゃがな、還暦の胃袋には自ずと限界はあるがな。山の空気自体が調味料じゃからの、全てが美味なのじゃ。その鮎の旬じゃがな、やはり宮崎のものは6月下旬から7月上旬でな、魯山人曰『鮎のうまいのは大きさからいうと、一寸五分ぐらいから四、五寸ぐらいまでのものである。それ以上大きく育ったものは、第一香気が失われ、大味でまずい。』のじゃからな、15cm前後のサイズということじゃ。吾輩も異論はないな。神門の小丸川は日本の清流100選の10数番目でな、川幅狭く流れも急峻じゃからな、魯山人の旨い処の総取りじゃ」
金之助「へええ、主人先生の生まれた故郷は猪ばかりじゃなかったんですにゃん?」
主人先生「それも知らんかったんか? 春の青々しい木の芽をたっぷり食らい、それを脂分に含ませた寒の猪、鹿フィレのチルドも、それに虎杖や独活(地元では鹿の角に似ることから『シカ』と呼ぶ)などの山菜など挙げれば切りがないのう。鮎じゃがのう、鮎の背越しに勝る山女の小さめのものもあるぞよ。地元では『柴ご』(しばご=小さい山女は柴の中から湧き出るように泳ぐことから)と呼ぶんじゃ。いやいや横道にそれているが、今回は魯山人の譚をせにゃならんかったな。そうじゃこの譚をしようとしたのはな、最近仙台から海鞘を新幹線で東京駅まで運んだというニュースを見てからなのじゃ」
つづく。8月28日。