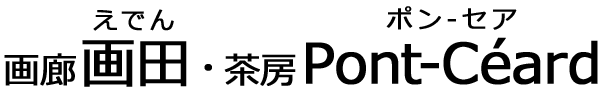●「信長公記に書かれた『比叡山を焼き打ち』」
▲叡山焼き討ちから450年、延暦寺を開いた天台宗の開祖・最澄が亡くなって1200年。最澄の教えは、「相手を許すことで、うらみを無くす」ことから、今回の法要で織田家と明智家の子孫を招待しての法要になったとの説明。叡山ともども、織田家と明智家が手打ちをしたことになる。(織田家と明智家が過去に会ったことがあるかは不明)。3者が同時に会って手打ちをしたことは、現世に生きている者は不憫ではないかもしれないが、信長、光秀、そして数千のあの世の犠牲者はとんだ迷惑だと不快ではなかろうか。ということで、下記は「信長公記」(太田牛一著・中川太古訳・新人物文庫)のなかで「比叡山焼き打ち」を、書き移してみた。
▲「(5)比叡山を焼き打ち
九月一二日、信長は比叡山を攻撃した。経緯は次のとおりである。
去年、信長が野田・福島を攻めて、もう少しで落城という時、越前の朝倉義景と北近江の浅井長政が坂本方面へ攻め寄せた。信長は『敵が京都洛中に侵入したら厄介なことになる』と言って、野田・福島の陣を引き払い、ただちに逢坂山を越え、越前・北近江勢に攻め掛かり、局笠山へ追い上げた。
兵糧攻めにする作戦で、延暦寺の僧衆を呼び寄せ、『このたび信長に味方をすれば、信長の領国中にある延暦寺領を元どおり返還する』旨を誓い、さらに朱印状を手渡して、『しかし、出家の道理で一方のみに味方することはできないと言うのであれば、我々の作戦行動を妨害しないでもらいたい』と筋道を立てて申し聞かせ、『もしもこの二カ条に違背したならば、根本中堂・日吉大社をはじめとして、一山ことごとくを焼き払うであろう』と言明したのであった。
比叡山の山上・山下の僧衆は、延暦寺が皇都の鎮守であるにもかかわらず、日常の行動でも仏道の修行でも出家の道をはずれ、天下の笑いものになっているのも恥じず、天の道に背くことの恐ろしさにも気づかず、色欲に耽り、生臭ものを食い、金銀の欲に溺れて、浅井・朝倉に加担し、勝手気ままな振るまいをしていた。けれども信長は、時の流れに従って、ひとまずは遠慮をし、事を荒立てぬよう、残念ながら兵を収めたのであった。
ついにその時がきたのであろうか。その鬱憤を今日こそ晴らすため、九月一二日、比叡山を攻撃し、根本中堂・日吉神社をはじめ、仏堂・神社、僧坊・経蔵、一棟も残さず、一挙に焼き払った。煙は雲霞の湧き上がるがごとく、無惨にも一山ことごとく灰燼の地と化した。
山下の老若男女は右往左往して逃げまどい、取るものも取りあえず、皆はだしのままで八王山へ逃げ上り、日吉大社の奥宮に逃げ込んだ。諸隊の兵は、四方から鬨の声をあげて攻め上った。僧・俗・児童・上人、すべての首を切り、信長の検分に供して、これは叡山を代表するほどの高僧であるとか、貴僧である、学識高い僧であるなどと言上した。そのほか美女・小童、数も知れぬほど捕らえ、信長の前に引き出した。悪僧はいうまでもなく、『私どもはお助けください』と口々に哀願する者たちも決して宥さず、一人残らず首を打ち落とした。哀れにも数千の死体がごろごろところがり、目も当てられぬ有様だった。
信長は、年来の鬱憤を晴らすことができた。そして、志賀郡を明智光秀に与え、明智は坂本に居城を構えたのである。
九月二十日、信長は美濃の岐阜に帰陣した。
九月二十一日、河尻秀隆・丹羽長秀の二人に命じ、高宮右京亮とその一族を佐和山へ出頭させ、殺害させた。抵抗して切りかかってきたが、造作もなく成敗した。その理由は、昨年、野田・福島の陣の時、高宮は大阪方に内通して一揆勢を蜂起させる謀略を働き、戦いの最中に川口の砦を脱走して大阪の城に駆け込んだからである。
【注】(1)野田・福島=大阪市福島区 (2)坂本=滋賀県大津市」
▲信長の生涯、戦をしない日は何日あったのだろうか。「信長公記」は、戦に明け暮れた信長の生誕から本能の変までの生涯を記述した一級史料。著者の太田牛一はその奥書で、「故意に削除したものはなく、創作もしていない。これが偽りであれば神罰を受けるであろう」と記している。「信長公記」が存在しなければ戦国の小説はどのような展開をみせたのであろうか。歴史に興味がある若者には必読の一級品。
9月18日。
●「Y遺伝子①」
▲自民党の総裁選が活況だ。候補者の一人である河野太郎氏の出馬会見には少々驚いた。会見の「日本の礎は長い伝統と歴史と文化に裏付けられた皇室と日本語」の一節である。私も日本語が大好きだからこうして飽きることなく日々、たわいのないことを綴っている。日本語のルーツは遠い弥生時代の紀元前3世紀ころであり、文法的にはアルタイ語系、発音はポリネシア系の影響が大であり、紀元後には卑弥呼以来に見られる中国漢字伝来※の恩恵を受けている(少なくとも魏志倭人伝に登場する卑弥呼の使者は、その時、漢字に接していた)。要は、弥生時代に米作と共に海を渡って来た”異国”からの人々の言語と、想像だが”原住”の縄文人言語とによる合作であると考えるほうが自然であろうか。「日本の礎」が「日本語」と言われると、なぜかしっくり腑に落ちない気がするのは小生だけだろうか。かりに「日本の礎は日本語をはじめとした多様なる文化」なら頷けないか。言語は文化のひとつであるからして(言語文化)。
※日本列島への漢字伝来の時期特定は容易ではないらしいが、物的証拠としては、稲荷山古墳から出土した鉄剣銘(471年)が我が国における漢字の初発であり、本格的な漢字使用は5世紀の初めころから、との学説あり。
▲「日本の礎は日本語」、気にかけないで聞き流すとしよう。では、「日本の礎は皇室」はどうだ。私は、皇室を否定する者でもなけらば、取りたてて奉り賛美する者でもない。為政者が最も識るように、天皇を事あるごとに操り、私利私略的に利用してきた歴史がある。先の大戦も明治維新も、日本の歴史の転換点において、天皇は「錦の旗」として常にその時の為政者によって利用され続けてきた。河野太郎氏は「女系天皇」を容認する国会議員のひとりでもある。出馬会見で、わざわざ皇室を持ち上げたのは怪しい。
▲その「女系天皇」についてである。説明は不要だろうが、歴史上日本の女性天皇は8人いた。第33代の推古天皇、第35の皇極天皇・37代の斉明天皇(両者は同一人物)、第41代の持統天皇、第43代の元明天皇、第44代の元正天皇、第46代の孝謙天皇・第48代の称徳天皇(両者は同一人物)、第109代の明正天皇、第117代の後桜町天皇の面々である。どなたもピンチヒッター的な即位である。なぜ中継ぎ役の女性天皇を必要としたのかは、諸皇子の候補擁立勢力の対立や天皇の夭逝(皇太子が幼少)が原因とされる。女性天皇はあくまで中継ぎのため、基本的には一代かぎりで、その後は必ず男性天皇が即位する”伝統”である。
▲女性天皇の一代限りは、性染色体がXXでY遺伝子を有しないことによる。イギリスの王女エリザベス2世は、むろん女性であるが、嗣子のチャールズ皇太子のY遺伝子はエリザベス女王の婿(フィリップ=エディンバラ公)に由来する。日本の皇室(皇室典範)は、天皇直系の男子のY遺伝子以外を認めていない。そうであるから、高市早苗総裁候補のように「天皇直系(Y遺伝子を有する)男子と愛子様との養子縁組」の発言がある。
▲この考えに固執するのは天皇に限ったことではないようだ。この9月12日、織田信長による比叡山延暦寺焼討から450年ということで織田信長と明智光秀の子孫を初めて招いての法要が営まれたとのニュース。この法要に招待された織田方は織田某氏、明智方からは明智某氏。どちらも男性である。織田某氏は信長の次男、信雄の男系子孫という。一方の明智某氏は光秀の子、於隺丸(おづるまる)の子孫であると私称しているが、於隺丸は実在不明の人物とされるなど直系に懐疑的な見方もあるようだ
▲信長を本能寺の変で自刃に追い込んだ明智光秀の子孫と云えば、いちばんに浮かぶのが元総理大臣の細川護熙氏であろう。周知のように明智光秀の子女、玉は細川忠興の妻であり、その細川家が加藤清正後の肥後藩の殿様となって幕末まで続き、第18代※の護熙氏が熊本県知事から首相になった。細川家は歴とした明智光秀の遺伝子を引き継ぐ名家であるが、その遺伝子はYではなくXである。むろん織田某氏は信長のY、信雄のYを遺伝している。
※肥後細川家の初代は、明智玉(細川ガラシャ・1563~1600)の夫・細川忠興(1563~1646)が初代。忠興は利休七哲の一人。
▲Y遺伝子の譚であるが、Y遺伝子に固執するのはなにも王家だけではないのである。つづく。
9月16日。
●「連載物の挿絵」
▲いまの日経新聞朝刊の連載小説は、安部龍太郎氏の「ふりさけ見れば」(主人公は遣唐使として中国に渡り、唐の玄宗皇帝に取り立てられ、異国で出世を遂げた阿倍仲麻呂)である。画は西のぼる氏。画とは挿絵(さしえ)のことである。数年前、神田の古本屋街を散策した折、某書店で「吾輩は猫である」の挿絵が額装で壁に掛けてあるのを目に留め、値札がなっかったが交渉で買った。店主は丁度敬老会で留守をしており、息子嫁さんと思しき人が応対してくれたのだが、他にもないかと問うと、裏から古い「吾輩は猫である」の単行本を取り出し、その中の挿絵を見せ2枚ほど選ばせてくれた。その時の3枚は今も私の額に収まっている。
▲「吾輩は猫である」の初版は1905年(明治38年10月3日印刷、同10月6日発行、発行所は大倉書店・服部書店)で、私の代物は明治40年版の第2版か第3版物であった。少なくとも昭和になって出された復刻版ではない。今を遡ること1世紀以上前の「吾輩は猫である」の単行本には、少ないが所々に色付の挿絵があるのである。その挿絵を買った私は、宮崎の某画廊を訪ね、額装にしてもらったのが掲載の写真である。「吾輩は猫である」の挿絵画家は、橋口五葉、中村不折、浅井忠。3人とも日本画からはじめて後に洋画家に転身した画伯である。写真の絵は、無論本画ではなく、単行本に印刷された、謂わば版画(印刷)というものであろうが、100年以上も前の「吾輩は猫である」には挿絵も入っていたのである。
▲漱石は、その一人の中村不折に対して、「発売の日からわずか20日で初版が売り切れ、それは不折の軽妙な挿絵のおかげであり、大いに売り上げの景気を助けてくれたことを感謝する」旨の手紙を送っている。その初版から僅かの期間をおいての第2版か第3版の挿絵が私のもとに存在するのである。鑑定団ものであろうか(そうではあるまいが)。
▲余談はさておき、「竜馬がゆく」の岩田専太郎の挿絵の譚である。先ずは日本橋の丸善に電話して「司馬遼太郎全集」の挿絵について問うたが、全集には挿絵は全くないとの返答。然らば神田の古本屋は如何にや、と云うことで最近世話になりはじめた神田の他の某書店へ問い合わせたところ同じ応えであった。それで万事休す。岩田専太郎画伯のあの妖艶な絵とは縁なくめぐり合わせがなかったという譚である。
▲今回は挿絵の譚である。漱石が挿絵の御蔭で本が売れたと画家に謝意を示したことの御蔭で今も新聞連載小説に毎回挿絵が載るようになったのではないのかと勘繰りたくもなるが・・・・・・。挿絵はサラッと描き流しの、一見何の変哲の無い平凡な画のようでありながら、実はそれこそ抜き差しならぬ魔力があると云う譚なのだ。想像だが、毎度々々締切ギリギリで回される原稿に即座に反応して画をしたためなければならないからこそ、読者は作家の文章に生な場面を想像しうるのであるろう。
9月13日。