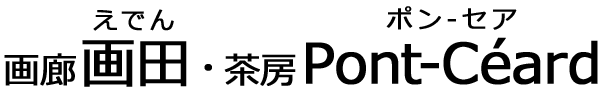春夏秋冬の季節の変わり目の前の18日間を土用と云う。季節の変わり目とは立夏、立秋、立冬、立春を指す。丑の日とは子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥の12支の「丑」の事。
今年の土用の丑の日は7月30日であるが、年によっては土用の期間中丑の日が2回ある。この場合には、最初の丑の日を土用の丑の日というようで、夏負け・夏痩せしないように鰻を食う習わしとなっている。
江戸時代、鰻屋のオヤジが夏場の商売が上がったりなので、知恵者であった平賀源内(1728~1779、エレキテルで有名。天才にして多才。日本の江戸期のレオナルド・ダ・ヴィンチとでも言おう)に相談したところ、「丑の日に「う」のつくものを食うと夏負けしない」という当時の民間伝承から、鰻屋の入口に「本日丑の日」と書いて貼るように進言したのがはじまりと云う。
ところで、鰻は相当昔から一般庶民に食されていた。奈良時代の歌人で三十六歌仙の一人、大伴旅人の子である大伴家持(やかもち)(717?~785)の歌に「岩麻呂(いわまろ)にわれもの申す。夏痩せによしといふものぞ。鰻漁り食せ(とりめせ)。」(万葉集)とある。当時は今のような蒲焼で食うのではなく、丸太切りで木か竹の棒に挿して焼いて食していたようだ。因みに蒲焼の語源は鰻を縦に串刺しにして丸焼にした形が蒲(がま)の穂ににているからだ。「ガマヤキ」の発音が変化して「カバヤキ」になった。
今風の蒲焼の形になったのは江戸後期のことで、それまでは味噌を使った丸焼きだった。関東では武士が切腹を嫌ったからか背開きで、白焼き(5分位)して蒸し(20分位)、さらにタレで3回ほど焼く。関西では腹開きで蒸さずに焼くだけだ。江戸時代は脂の乗った鰻は肉体労働者の食するものであった。蒸すのはその脂を落として減らすためだ。
宮崎(全国の15.1%、2006年農水省まとめ)は養殖鰻の生産量が鹿児島(33.7%)、愛知(33.2%)に次いで3番目である。浜名湖で有名な静岡県は、湖の塩分濃度の上昇などが原因して最盛期の1割弱(1400トン)まで減少し、4番手(6.9%)にある。宮崎の蒲焼も捨てたものではないが、タレが宮崎料理特有に甘すぎるのがやや気に入らない。肝吸が付いてこないのには合点がいかない。蒲焼の濃さと吸い物の軽さ、肝の苦味とのマッチが何ともいい。少なくとも呉汁との二者択一にして貰いたい。鰻がゴムのようなモノや、豚汁が出てくる店は論外である。白飯も水分の多いネチネチではなく、タレが鰻重の飯の半分位まで浸み込むような、丁度の硬さがよい。米も蒲焼に引けを取らない位上等でないと旨みは半減する。
宮崎では肝吸を出す店が少ないが、そのお陰で良いこともある。最近、居酒屋で鰻の肝焼き(胆嚢を含む)を出してくれる。安価であの鰻独特の胆汁酸の苦味が焼酎の量を増やす。鰻肝にはVitaminAが豊富だ。ウナギの語源はその「長い身(うなみ)」の変化と云う。この身には夏バテに良いVitaminB群と良質の蛋白が豊富だ。鰻の本当の旬は脂の乗った秋である。産卵のため海に向かう天然の下り鰻が絶品とされる。小生は養殖鰻の背開きで脂を中等度に落とした蒸さない、しかもタレの甘くないのが好みだ。無論、吸い物は肝吸でないといけない。東京銀座1丁目で食った「ひょうたん屋」(東京では珍しい関西風、TEL03-3561-5615、やわらか鰻でさっぱりタレ、うな重・特上2.200円、細かな気配りが詰まった極上の味)の鰻重には殊の外満足させて貰った。
鰻の蒲焼が日本の食文化から消滅していくようなことが有ってはならない。中国などの輸入物が約8割を占めるが、薬物使用などで問題化している。宮崎の鰻がブランド化され、そして中央からも脚光を浴びる日が来るよう、県民皆で知恵を絞らないといけない。年に何度も食わない鰻だから、土用の期間ぐらいは量の「特上」ではなく質の「特上」を食っても罰はあたるまい。「バレンタイン・デー」の如くに1日限りの祭り事に止まらず、各季節の土用の18日間に1度は鰻屋に出かけて精を付けようではありませんか。