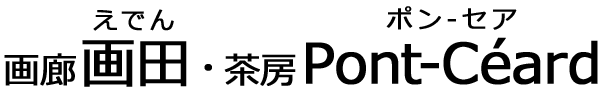最近の「医療崩壊」について、いろいろと講釈を垂れたいことも少なくないが、最近嬉しいテレビ報道をみた。助産師さんが復活し、活躍の場を拡げている。例えば、産婦人科病院に数名の助産師さんがいて、24時間体制でお産を介助し、妊婦が安心して分娩できるシステムである。お産前に正常な分娩が可能と思われるものの9割が、医師の特別な手を借りることなく、助産師のみでの分娩が可能という。
医師の責任の程度は専門科によって異なる。心筋梗塞、狭心症、動脈瘤、脳梗塞、脳出血、交通事故などによる外傷、そして問題の「小児とお産医療」は緊急にして重労働である。医師の中でも「外科医」と「小児科医」、「産科医」にかかる負担は特に重い。
獣医療でもまったく同じで、たとえば夜中の帝王切開は、スタッフが揃わないこともあるが、その後の数日間は体調(バイオリズム)が狂う。これは術中や処置中の「極度の緊張」に因る。「生きるか死ぬか」、「救えるか、否か」は「天と地」の差。患者と家族、それに医師や獣医師にとっても「天国と地獄」である。医師や獣医師も「生身の人間」である。時間外救急の切迫した状況は、昼間の通常診療にも影響を及ぼすようになる。患者も行政も、そして医師会も、医師一人ひとりが「生身の人間」であることをまず理解しなくてはならない。「医療崩壊」の原因はいろいろあろうが、解決するには情勢分析が欠かせない。「天命や使命」の遂行にも「生身の人間」であることの「壁」があるのだ。
小生は3人兄弟で、3人とも家の縁側で生まれた。おふくろは昭和12年(1937年)生まれで、一昨年金婚式を迎えた。もう50年も前の昔話になるが、小生のお産時に子宮からの出血が止まらなかった。産婆さんは、「唐米袋(とうまいぶくろ=玄米を入れる麻袋)に庭先の畑の土を詰めてくるよう」、親父に指示し、その袋を下腹部に押し当てて止血したそうだ。産婆さんの機転がきかなかったら、お袋の命は多分になかったであろう。お産には故・曾祖母(5人の子供を出産)と故・祖母2人(どちらも7人の子供を出産)が助手として立会い、親父は2歳年上の兄貴を背負って、庭を「あっちこっち、うろちょろ」していたそうである。
産婆さんは江戸時代からいたそうで、古くは「取り上げ婆(ばばあ)」と呼ばれ、戦前までは「産婆」、戦後は「助産婦」、そして現在の「助産師」に至っている。一時は正常分娩でも医師のいる産婦人科病院での分娩が主流であったが、ここにきてまた「助産師」が台頭し最前線で復活しているから、頼もしく、嬉しいことだ。「命」にかかわる仕事は、辛い反面、喜びも一入(ひとしお)である。半世紀前の「天使の産婆さん」、いやいや失礼、「天使の助産師」さんに感謝である。経験は知識を凌駕することを、これまたよく「経験」する。故・曽祖母と両祖母(こちらは本当の「三婆さん」かもしれないが)にも、懐旧の念をもって、感謝である。