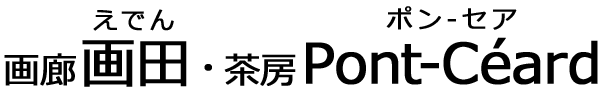●蛍の灯(続編)
金之助「スコッチは『竹鶴』でしょうか、『岩井』でよいのでしょうか。歌の文句に、『あっちの水は苦いぞ、こっちの水は甘いぞ』なんてありますが、辛い水でよいのですにゃん」
主人先生「分かり切っているのに念を押すとは、なかなかの忠誠もんじゃな。ところで金之助よ、万葉の時代の螢は忌み嫌われていたのじゃが、平安や鎌倉、そして江戸ともなれば大分好もしいものに様変わりしてきたのじゃ。そうじゃ、鑑賞の対象となっていったのじゃな。ひとつ目は源氏物語じゃが、五十四帖の第二十五帖に『螢』があり、『源氏は几帳の中に蛍を放ってその光で玉鬘の姿を浮かび上がらせた。』とあるんじゃ。まるで『蛍雪』のようじゃな。次いで『太平記』にも螢が出てくるのじゃがこれはあとでゆるりと語ろうぞ。3つ目が、小林一茶の俳句じゃ。『大蛍ゆらりゆらりと通りけり』・・・・・・なんて何とも風情の極みとしての螢がじゃな。日本を代表する文学に遺されているのじゃから驚愕ものじゃ。先人の天才達に感謝じゃな」
金之助「なんですか、『太平記』とは。いつぞか大河ドラマかなにかで聞いたような名前ですが。そうじゃった、いま主人先生が熱くはまっている山岡荘八の『新太平記』じゃったにゃん」
主人先生「主人の日常をよく観ているのお、金之助君よ。その『新太平記』のなかにな、『ご不例の主上を近々お招きし、宇治の里からおびただしい蛍を運んで来て、青葉の庭から池のほとりに放って気鬱を慰めようというのであった。』(山岡荘八『新太平記3・建武中興の巻』p391・講談社)とか、『ぬばたまの暗にちりばめられてゆく蛍の光の美しさは、思うだけで涼を呼ぶに充分だった。』(同p406)、とあるんじゃ。しかしこの螢鑑賞のシチュエーションは雅なものとは程遠く、実際は、大納言西園寺公宗が主上の後醍醐天皇を謀殺するためのひとつの設定に利用されたのじゃがな。この計画は直前に漏れて失敗に終わるのじゃが」
金之助「今回もまたまた歴史の講義じゃにゃんか? 吾輩の興味はやはり一茶にござるな。『大蛍ゆらりゆらりと通りけり』・・・・・・この蛍じゃと優しく吾輩ともいつまでも遊び戯れてくれそうにゃん。この一茶の世界じゃと黄泉(あの世)でも寂しくなさそうにゃん」
主人先生「猫の分際で一茶を解する何ぞ、流石は漱石先生の名をもらっただけあるな。ひとつ講釈を垂れていいかの。この螢の句はな、文政2年(1819年)ころの作とされているのじゃが、一茶はこの9年後の文政10年11月19日に永眠したのじゃ。65歳じゃった。吾輩はな、藤沢周平の『一茶』に感銘を受け、奥信濃の生家(長野県柏原)を訪ねたくらいじゃ。当時の65歳は長生きじゃからの、この螢を詠んだ56歳頃は、まだ中風に罹る2年ほど前なので、元気じゃったと推測されるがのお。金之助の云うように、元気じゃからこそ黄泉を意識して、ゆらりと飛翔する源氏ボタルに死後の我が身を映したのであろうの。一茶の現身は、ゆらりの境地とは正反対の壮絶でスピード感極まる一生であったのじゃが」
金之助「そうであるにゃんか??・・・・・・ところで主人先生よ、妙なブログに熱中していて診療のほうは大丈夫にゃん? ここらで一茶ならぬ、コーヒーブレイクしてみゃーせんか?」
(完) 7月3日。